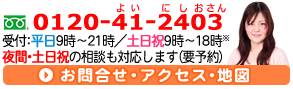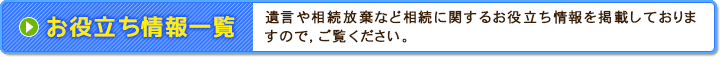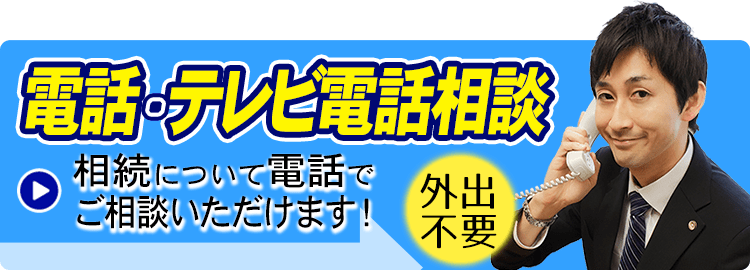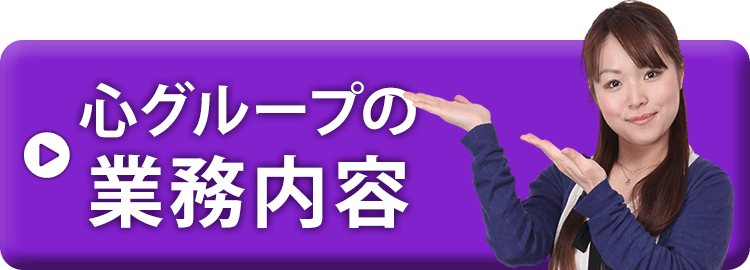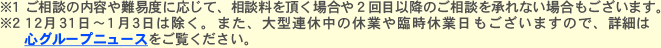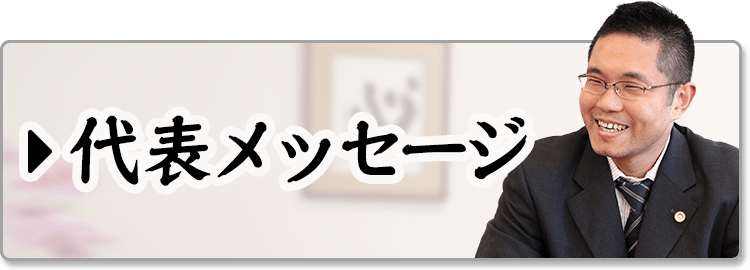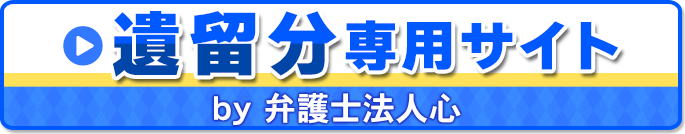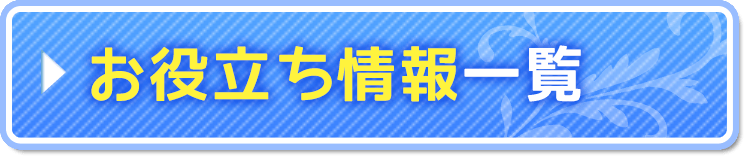相続と「縁を切る」ことについてのQ&A
法律的に縁を切ることはできますか?
「縁切り」という制度は、法律上は存在しません。
そのため、何も対策をしないと、相続人全員で話し合いをする必要が出てきてしまうことがあります。
何年も連絡を取っていない親族でも縁は切れませんか?
相続人は、血のつながりで決まるため、どれだけ疎遠な親族でも、法定相続人である以上は、相続の権利があります。
ただし、相続人の一人が親の介護をしていて、他の相続人が一切連絡もしていなかった場合は、介護をした相続人の相続分が増える結果として疎遠な相続人の取り分が減ることはあります。
結婚して名字が変わった場合にも財産を渡さなければいけませんか?
原則、結婚して結婚相手の名字になっていても、亡くなった方と血縁関係がある以上は、相続権があります。
これは、女性が夫の姓を名乗るときだけでなく、男性が妻の姓を名乗るときも同じです。
ただし、次の質問にある特別養子縁組の場合は別です。
養子に行った親族にも相続権はありますか?
普通養子縁組の場合は、産みの親との関係でも血縁関係が残るため、相続権があります。
つまり、養子は、養親(=養子に行った先の親)の子供であると同時に、産みの親の子供でもあります。
一方で、特別養子縁組の場合は、産みの親との血縁関係が切れるため、産みの親の親族が亡くなったときに相続人となることはできません。
参考リンク:法務省・養子縁組について知ろう
親に借金があるのですが、生前に縁を切れませんか?
生前に縁を切って、親から子に借金が行かないようにするには、特別養子縁組で親との縁を切るしかありません。
一方で、親が亡くなってから3か月以内に相続放棄をすることで、借金を相続しないで済みます。
そのため、自分から相続を拒否する場合は、亡くなってから相続放棄をするのが簡単です。
財産を相続人に渡したくないのですが、どうすればいいですか?
遺言書を書くことで、財産を渡さないことができます。
ただし、配偶者(夫、妻)や子・孫には遺留分があるため、渡す財産をゼロにすることは難しいです。
一方で、亡くなった方の兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹に渡す財産をゼロにすることは不可能ではありません。
被相続人が保証人になっているかもしれないのですが,どうすればよいですか? 相続の生前対策に関するQ&A